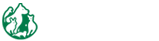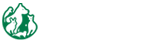by 佐藤華奈子 2025.11.17

野生動物の世界でも、調査技術の発展と日々の研究によって次々と新しい事実がわかっています。オオカミも例外ではなく、今までの絵本や昔話のイメージのままでいたら……すでに時代遅れになっている可能性もあります。わたしたちがイメージするオオカミの姿は、どこまで正しいのでしょうか。その特徴や生態を知って、知識をアップデートしましょう。
オオカミってどんなどうぶつ?

一般にオオカミというと、イヌ科イヌ属のハイイロオオカミを指します。ハイイロオオカミはタイリクオオカミとも呼ばれ、イヌ科の中で最も大きい仲間です。平均的な大きさは全長約130~200cm、体重約27~50kg。北部の寒いところに住むものほど大きくなる傾向があります。体の色は基本的にグレーや、茶色がかったグレーですが、黒や白の場合もあります。
ハイイロオオカミは北極圏やヨーロッパ、北アメリカ、アジアと北半球の広い範囲に生息。ツンドラでも砂漠でも、グレートプレーンズや温帯雨林でも見られ、各地のさまざまな環境に適応しています。
平均5~10頭の群れで生活し、狩りも仲間と協力して行います。おもな獲物はシカやヘラジカ、カリブー、バイソンなど蹄のある大型の草食動物。ビーバーやノウサギ、ネズミなど中~小型のほ乳類や鳥、は虫類、魚、果物を食べて足りない分を補うこともあります。群れごとに縄張りの範囲が決まっていて、その中で狩りをして洞窟や地面に掘った穴をねぐらにします。冬眠はしません。天敵がいない頂点捕食者で、生態系のバランスを保つためにとても重要な存在です。
野生下の平均寿命は6~8年ほど。13年ほど長生きすることもあります。飼育下の平均寿命は約15年です。
オオカミのよくある誤解

オオカミについて、よくある誤解と事実を紹介します。
月に向かって吠えるって本当?
オオカミといえば、月に向かって遠吠えをするイメージがあります。満月の夜には特によく吠えるともいわれますが、実際はどうなのでしょうか。オオカミが遠吠えをするのは、ほかのオオカミに呼びかけるため。別の群れに縄張りを主張したり、離れた場所にいる仲間に自分の位置を知らせたりしています。一頭が遠吠えをすると、仲間が呼応して次々に吠えていくこともあります。オオカミ同士のコミュニケーションとして行うため、月に向かって吠えることはありません。また、満月の夜に特別多く吠えることもないようです。遠吠えが満月に多いイメージができたのは、月が出ている夜にオオカミが遠吠えをする姿が印象的なためと考えられています。月が明るい夜は人も外で活動することが多く、このタイミングで遠吠えの声がよく聞かれたことも関係しているのでしょう。
群れの中に厳格な序列がある?
群れで行動するオオカミは、群れの中で序列が決まっていて、地位によって役割も分担されていると考えられていました。順位は厳格に守られ、定期的に確認されるともいわれています。ところがこれは、飼育下のオオカミの関係性を研究したもの。自然のオオカミの群れはもっと自由なことがわかっています。 野生のオオカミの群れは家族を単位としたもので、リーダー以外に、はっきりとした階層はみられません。群れを構成するのは親のペアと、その親から生まれて大人になった子どもたち。母親が出産すると、交代で子育てを手伝います。繁殖ができるのはリーダーのペアのみともいわれてきましたが、大きな群れや食べるものが十分にある環境では、リーダー以外のペアも繁殖することがあります。
ちなみにオオカミの関係性で最も厳格なものは夫婦の絆。一度ペアになると、死別するまで一緒に行動します。残された側がその死を悼むような行動をすることもよく観察されています。
狂暴な性格で人を襲う?
野生のオオカミは人を襲うというイメージがありますが、実際はほとんど人に襲いかかることはないといいます。人間はオオカミの本来の獲物ではありません。また警戒心が高いため人と遭遇しても避ける傾向にあります。例外となるのは、食料が不足したときや、人間から攻撃を受けたとき。家族想いのため、群れの仲間のために闘うこともあります。狂犬病にかかって襲いかかったり、家畜を狙ったりすることもあるため、狂暴というイメージができたのかもしれません。それもすべてオオカミの仕業ではなく、野犬だった可能性もあるといわれています。
オオカミは絶滅危惧種?
ハイイロオオカミは、過去には大幅に数が減ったこともありますが、今も世界中に幅広く生息しており、現時点で絶滅の危険は低いとされています。ただ生息地によってはその場所で絶滅する恐れがあるケースもあります。オオカミの数が減る原因は開発によって生息地が少なくなることや、人間に迫害されることです。家畜を襲うこともあるため、駆除の対象となったこともあります。今では多くの生息地でオオカミの生態系における役割が見直され、絶滅した場所に再導入して数が増えているところもあります。家畜がいる場所との住み分けも試みられていますが、依然として農家の抵抗が強いところもあり、共存に向けた取り組みが続いています。
日本のオオカミはいつからいなくなった?

日本には昔、ニホンオオカミが生息していました。ニホンオオカミはほかのオオカミと比べて体が小さく、体重約15kgと中型犬くらいのサイズでした。1905年を最後に目撃情報が途絶え、絶滅とされました。絶滅の原因はひとつではなく、生息地の減少、人間による駆除、狂犬病やジステンパーといった感染症の流行など、さまざまな要因が重なった結果と考えられています。
日本ではオオカミは古くから神聖なものと崇められてきました。農作物を荒らすシカやイノシシを食べることから、守り神のような存在となっていたのです。ところが時代が進んで西洋の価値観が入ってくると、オオカミは悪いもの、怖いものというイメージが浸透していきました。こうしたイメージの変化も、オオカミの駆除に拍車をかけた一因といわれています。
まとめ

二ホンオオカミの最後の目撃から100年以上経ちました。日本の山では今、シカやイノシシといった草食動物の数が増え、人里に降りて農作物やゴミまで食べてしまうことが問題になっています。オオカミがいなくなった場所では、世界中どこでも同じようなことが起こっています。地球上のどこでも、オオカミが生態系にとって重要な存在であることは変わりません。今では世界中の生息地でオオカミの役割が理解され、保護されつつあります。わたしたちもオオカミと同じことを繰り返さないために、一方的なイメージで野生動物を決めつけるのではなく、正しい知識を持って見守っていきたいですね。