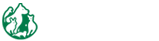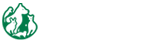by 佐藤華奈子 2025.10.15

背中に独特のコブがあるラクダ。砂漠で荷物を載せて長距離を歩けるため「砂漠の船」として交易で活躍してきました。ほかのどうぶつでは難しいことが、なぜラクダはできてしまうのでしょうか。ラクダのすごいところを紹介します。
ラクダってどんなどうぶつ?

ラクダはラクダ科ラクダ属の仲間の総称です。背中のコブが特徴で、コブの数でヒトコブラクダとフタコブラクダに分けられます。3000年以上前から人に飼われるようになり、中東やアフリカ、アジアの砂漠で荷物を運んだり人を乗せたりして活躍してきました。
現在、世界にいるラクダはほぼ家畜として飼われているもので、野生のラクダはごくわずか。野生のヒトコブラクダは絶滅しました。フタコブラクダも野生のものは絶滅危惧種に指定されています。
ラクダの特徴
体高は2mを超え、体重は350〜700kgにもなります。背中のコブの中には脂肪が蓄えられ、栄養が不足したときはここから補います。コブのおかげで何日も食べなくても動くことができるのです。中の脂肪が使われて少なくなると、コブはしぼんで横に倒れます。高齢のラクダもコブがやせて倒れています。
ラクダが食べるもの
完全な草食で草を食べます。ウシと同じ反芻動物で3つの胃があります。
動物園では牧草や草食動物用のペレット、野菜を食べています。
ラクダの性格
性格はやさしく温厚。人のいうことをよく聞いてくれます。怒ったときや警戒しているときは唾を飛ばすことがあります。
ラクダの寿命
平均的な寿命は30年前後です。長いものでは50年近く生きることもあります。
ラクダのすごいところ6選!

砂漠の過酷な気候に適応したラクダの体には、コブのほかにもすごいところがたくさんあります。
正常体温の幅がすごい!
昼夜の寒暖差が激しい砂漠では、日中の気温は40度を超えるのに、夜間は10度を下回ることもあります。冬の夜間は氷点下になることも。そんな環境で暮らすラクダの正常体温は、34~40度と大きな幅があります。人間が汗をかき、イヌなら舌を出して息をするような気温でも、ラクダは涼しい顔をしています。体温が正常範囲を超えると、汗をかいて体温を下げる必要があります。ラクダは汗で貴重な水分が失われないように、体温の正常範囲を上げたのです。
体温が大幅に上下しても、脳の温度だけは一定に保たれています。その秘密は長い鼻にあります。乾燥した空気を吸い込むと、鼻の中の水分が蒸発し、気化熱で温度が下がります。これで鼻の近くを通る血管の血液を冷やし、脳の温度を保っているそうです。
砂への適応がすごい!
大きな体に100kgを超える荷物を載せて砂漠を歩くラクダ。その速度は馬が歩く速さと変わらないといいます。砂に足をとられてしまうことはないのでしょうか。ラクダの足は蹄が大きく、足底に柔らかいクッションがあります。そのおかげで体重を分散でき、砂に沈みにくいようになっています。
また、耳には砂が入らないようにびっしりと毛が生えています。鼻の穴を閉じることができるので、鼻に砂が入ることもありません。目は長いまつ毛で守られ、瞬膜という薄い膜を閉じることで、砂嵐の中でも視界を維持しながら目を守ることが可能です。さらに脂肪分を多く含んだ涙で乾燥から保護しているため、大きな目はうるんで見えます。
一度に飲む水の量がすごい!
何日も水を飲まなくても生きられるラクダ。なぜそんなことができるのでしょうか。コブの脂肪を分解して水に変えることもできますが、その量はごくわずか。基本的におしっこの量を少なくすること、汗をほとんどかかないことで体から出ていく水分を極限まで少なくしています。さらに鼻の穴をふさぐことで、呼吸による水分の蒸発も防止。そして水を飲む機会が少ない分、飲めるときに一気に大量に飲んでいます。その量はなんと約100リットル!人間が水を一度に大量摂取すると、血液の浸透圧が低くなり、赤血球が破壊されてしまいます。ところがラクダの赤血球は2倍まで膨れあがることができ、簡単に破壊されることはありません。赤血球の形は丸ではなく楕円形で、逆に血中の水分が少なくなっても血球の流れが滞りにくくなっています。細胞レベルで砂漠の乾燥に適応しているのですね。
サボテンも食べられる!

砂漠の植物といえばサボテン。ラクダはなんとトゲがあるサボテンまで平気で食べてしまいます。唇が分厚く丈夫なうえ、口の中に特殊な突起があるからです。この突起が食べたものを一方向にそろえる働きをするので、トゲが口の中で刺さりにくいのだそう。痛みを我慢しているわけではなさそうです。
ミルクの栄養がすごい!
ラクダは荷物の運搬だけでなく、ミルクも飲料として重宝されてきました。ラクダのミルクは牛乳よりも脂肪や乳糖が少なく、ビタミンCや鉄分、ビタミンB群などの栄養素が豊富に含まれています。砂漠の遊牧民の間で「ラクダのミルクだけで1ヶ月生きられる」といわれるほどです。味は牛乳よりすっきりして、ほのかに塩味を感じるといいます。
江戸時代の人気がすごい!
ラクダが初めて日本に来たのは、江戸時代のことです。1821年に一組のつがいが長崎に入り、西日本各地を巡業。東海道を歩いて江戸にもやってきました。外国のどうぶつを見る機会がなかった当時、観覧料が高くても大変な人気で人だかりができたといいます。最終的な興行収入は莫大な額になり、ラクダの姿を描いた錦絵など関連グッズも売られていたのだとか。夫婦仲良く並んで歩いていたことから、ラクダを見ると夫婦円満のご利益があるともいわれました。
まとめ

厳しい環境に適応して進化したラクダたち。今、世界中の農業、畜産業が気候変動の影響を受ける中、適応力が高いラクダに注目が集まっています。
世界のラクダの飼育頭数は、2001年時点の推定2,200万頭が2021年には3,900万頭に。2000年代に入ってからの20年間で倍増し、その後も増加傾向にあるといいます。ラクダのミルクを飲む習慣がなかった国でも、農場でラクダを飼育してミルクを生産する事業が始まっています。日本でもいつかラクダのミルクが普及するかも?ラクダの今後にも注目したいですね。