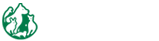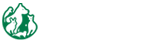by 佐藤華奈子 2025.07.16

大きな丸い瞳のアザラシ。流氷の上でお昼寝する姿はとても幸せそうで、見ているだけで癒されます。そんな野生のアザラシは、一体どこにいてどんな風に生きているのでしょうか? かわいくて癒されるからこそ気になる、アザラシのよくある疑問を解消します。
アザラシは何の仲間?
海獣と呼ばれる海で暮らすほ乳類のひとつであるアザラシ。分類上はどんなどうぶつの仲間なのでしょうか。
アザラシは鰭脚(ききゃく)類に分類され、19種の仲間がいます。鰭脚類は「鰭(ヒレ)がある脚」を意味し、その名の通り脚がヒレのような形をしています。
アザラシが属する鰭脚類は、食肉目に分類されます。食肉目にはクマやイヌ、ネコ、イタチなど多くの肉食動物がいます。つまり、大きなくくりで見るとこれらの仲間になります。ちなみに、クジラやイルカはウシやヒツジと同じ偶蹄(ぐうてい)目の仲間で、ジュゴンやマナティは海牛(かいぎゅう)目の仲間。同じ海に生きるほ乳類よりも、陸上にいるクマやイヌの方が近い関係にあるのです。アザラシのお顔をよく見ると、大きな丸い目にヒゲがある口元はネコに似た雰囲気がありますね。性格は好奇心旺盛で遊び心があり、人にも懐くことから「海の犬」と呼ばれることもあります。
アシカやオットセイとは何が違う

では、アシカやオットセイとは何が違うのでしょうか? 分類から見ていくと、アシカもオットセイも、さらにはセイウチもアザラシと同じ鰭脚類の仲間です。鰭脚類の中にアザラシ科とアシカ科、セイウチ科があり、アシカ科の中にアシカとオットセイがいます。トドもアシカ科です。
外見の違いも見ていきましょう。まず、アザラシの耳はただ穴が開いているだけで、耳介(じかい)と呼ばれる外側に出ている耳がありません。一方で、アシカやオットセイは穴のまわりに小さな耳がついています。英語ではアザラシ科を「耳のないアザラシ(earless seals)」、アシカ科を「耳があるアザラシ(eared seals)」と呼んで区別することもあります。
移動の方法も異なります。アザラシは体に対して足が小さく、陸上では常に腹ばいです。前足をバタバタと必死に動かしたり、滑ったり転がったりすることで移動します。何とも愛らしい移動方法ですね。変わってアシカは、体に対して大きめの足で、前後の足を器用に動かしてスムーズに歩くことができます。足で全体重を支えて体を浮かせることもできてしまいます。陸上ではアシカの方が速く動けますが、水に入るとアザラシの方が速く泳げます。アザラシ科は潜水も得意で、品種によっては1,500mの深さまで、2時間もの間潜水できるものも。泳ぎ方も異なり、アザラシは後足を使って泳ぎますが、アシカは前足を動かして泳ぎます。
アザラシはどこにいる?
アザラシの生息場所は種によって異なりますが、多くは南極や北極の冷たい海に暮らしています。同じ場所に定住せず、回遊する種類もいて、外洋でも、沿岸でも見られます。ロシアのバイカル湖には唯一の淡水に住むアザラシ、バイカルアザラシがいます。
日本には、回遊でやってくるアザラシと定住しているアザラシがいます。いずれも北海道で見られます。定住しているのは、襟裳岬など太平洋側に生息するゼニガタアザラシ。体に昔の穴あき硬貨のような模様があることからこの名前になりました。世界中の幅広い範囲で見られるアザラシです。そしてゴマフアザラシ、ワモンアザラシ、アゴヒゲアザラシ、クラカケアザラシが回遊で日本の海を訪れます。
アザラシは何を食べる?
アザラシは肉食で、基本的に海で魚や軟体動物、甲殻類を獲って食べています。食べるときは噛まずに丸飲み。味覚は退化して味を感じることはありません。海で捕れるものを何でも食べる傾向があり、食べる種類に偏りやこだわりは見られないようです。一部例外もあり、たとえばヒョウアザラシは魚だけでなくほかのアザラシやペンギンを捕まえて食べることがあります。また、カニクイアザラシは名に反してカニは食べず、オキアミという小さな甲殻類を独自に進化した歯で漉しとって食べています。
体の大きさはどのくらい?
体の大きさも種によって異なります。最小のバイカルアザラシは体長110~140㎝、体重は50~100㎏ほど。最大のミナミゾウアザラシは、大きなものでは体長が7mにもおよび、体重は4,000㎏を超えることも。よく名前を聞くゴマフアザラシは、体長140~170㎝、体重は70~115㎏ほど。日本にも生息すると紹介したゼニガタアザラシは体長150~190㎝、体重は65~170㎏ほどになります。
体が丸々しているのはなぜ?

アザラシといえば、丸々とした体。その秘密は脂肪で、体脂肪率が50%を超えることもあります。脂肪の役割は、ただエネルギーを蓄えるだけではありません。冷たい海で生きるために、断熱材のような役割も果たしています。また泳ぐときに浮力も与えてくれます。
どんな1日を過ごしている?
アザラシは繁殖の時期以外は基本的に単独行動。泳ぐことに適した体をしていますが、一生を通して見ると大半は陸で過ごしています。水に潜るのは食べるものを探すため。陸に上がるのは休憩や出産のためで、出産や子育ての時以外は、陸や流氷の上でゴロゴロして日光浴をしたり、休んだり、眠ったりして過ごしています。陸にいるアザラシを見ると、とても幸せな1日に見えますね。
ただ、アザラシにはシャチやホッキョクグマ、ヒョウアザラシ、大きなサメなど天敵もいて、それを警戒しながら生きています。ミナミゾウアザラシのように脂肪たっぷりの体を維持するために、1日のほとんど、20時間ほどを食べ物探しに費やす場合もあります。陸にいる姿を見るだけではわからない苦労があるかもしれません。
アザラシは絶滅危惧種?
すべての種ではありませんが、一部のアザラシは絶滅危惧種に指定されています。アザラシは毛皮や肉のために狩猟の対象となり、そのために絶滅してしまった種もあります。今では狩猟は規制されていますが、漁具に絡まってケガをすることや、食料の採取地が人間の漁場と重なることなど、変わらず人間の活動によって絶滅の危機にさらされています。特に大きな脅威と考えられているのは気候変動で、流氷が溶けて少なくなることでアザラシの繁殖や食料採取に問題が起こることが懸念されます。
まとめ

かわいいアザラシは遠い南極や北極だけでなく、日本の海にもいる野生動物です。アザラシが住む海を守りながら、これからも共存できるように、わたしたちも日々の生活の中で環境を意識して、できることを考えていきたいですね。