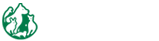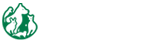by 佐藤華奈子 2025.09.03

イノシシは西日本の山を中心に広く生息する身近な野生動物。近年は人里に現れることが増え、農作物の被害が深刻になっています。この問題を考えるためにも、イノシシの生態や特徴を知っておきましょう。
イノシシってどんなどうぶつ?

イノシシは鯨偶蹄目イノシシ科の仲間。ブタの祖先で、分類上はブタもイノシシとブタの間に生まれたイノブタも同じ種になります。本来の生息地は日本を含むアジア、北アフリカ、ヨーロッパ全土ですが、今では外来種として南極を除くすべての大陸に広がっています。世界で最も繁栄する有蹄類(ゆうているい・ひづめを持つどうぶつ)といわれ、IUCN(国際自然保護連合)が選定した「世界の侵略的外来種ワースト100」の1つでもあります。草食よりの雑食で食べられるものの幅が広く、適応力が高いためです。「補食者から隠れられる茂みがある」「飲用と体をきれいにする水がある」「定期的な降雪がない」という条件がそろうと急激に数が増えることがあるといいます。
本来の生息地も幅広いことから、生息場所によっていくつかの亜種に分けられています。日本には二ホンイノシシとリュウキュウイノシシという亜種がいます。西日本を中心とした本州、四国、九州に二ホンイノシシ、沖縄と周辺の島にリュウキュウイノシシが生息しています。北海道にはいませんが、外来種としてイノブタが確認されました。
二ホンイノシシは体長100~170cm、体重は80~190㎏ほど。体色は茶褐色から灰色です。野生下の寿命は10歳ほどですが、多くは1~2歳までで命を落とします。以前は東北ではほとんど見られませんでしたが、近年、生息域が北へ広がり、それまでいなかった地域でも生息が確認されるようになりました。本来の食事はイネ科の草やヤマイモ・クズの根、ドングリ、果実、昆虫やミミズなどです。このほかにも農作物や生ごみを荒らして食べてしまうことがあり、各地で問題となっています。
イノシシのマメ知識

知っておきたいイノシシのマメ知識を紹介します。
母親と子どもで群れになる
イノシシは母親とその子どもで群れを作ります。男の子は大人になると自立して単独で暮らしますが、女の子は群れに残ることがあります。母と娘、姉妹とその子どもたちで十数頭の群れになることも。秋から冬にかけて繁殖期を迎え、春から初夏に4~5頭の赤ちゃんを産みます。出産がうまくいかなかった場合、春にも発情して秋に出産することもあります。
赤ちゃんは体の模様が縞瓜に似ていることから「ウリ坊」と呼ばれます。この縞模様は生後6ヶ月ごろに消えて大人と同じ見た目になります。
泥浴びで体をきれいにする
イノシシの習性として泥浴びが知られています。体表の寄生虫を落とすための行動と考えられています。泥浴びをする場所は「ぬた場」と呼ばれ、山の中で大きな水たまりのような場所が見つかるほか、水田や畑の水たまりを利用することも。ぬた場の周りの木には、体についた泥をこすりつけて落とした跡がみられます。
鼻の力が強い
イノシシはほかの有蹄類と比べて原始的な特徴をもち、視力はあまりよくありません。代わりに嗅覚が優れています。
鼻は臭いを嗅ぐだけでなく、物を持ち上げたり押したりすることにも使われます。その力はとても強く、60㎏のものを押し上げられるほどです。この力強い鼻を使って、食べるものを探したり、巣を作ったりするために地面を掘り起こします。その行動のおかげで、山の中に新しい植物が育つスペースが生まれます。また掘り返された種を鳥が食べたり、土の中に虫が卵を産んだりと、山の生態系に重要な役割を担っています。
「猪突猛進」は猟師が目撃した様子から
「猪突猛進」とは、イノシシが突進する姿や、それになぞらえてなりふり構わず一直線に突き進むことを意味します。イノシシの体は鎧のようにがっしりとした筋肉で覆われていて、時速約45㎞での突進こそが、最強の戦い方なのです。
イノシシ同士がケンカをするときは基本的に鋭い牙を使います。猪突猛進が見られるのは危険が迫り、猛スピードで走らざるを得ない状況になったとき。猟師に追い詰められたときなどがまさにそのような状況で、突進する姿が多く目撃されたことから、この言葉が生まれました。
この言葉のイメージから「まっすぐにしか走れない」と思われがちですが、実は方向転換も得意で、猛スピードで曲がることもあります。「後ろに進めない」と思われることもありますが、後退もできます。でも急に止まることは苦手です。
性格は慎重で賢い
突進する姿から勇猛果敢なイメージを持たれるイノシシですが、実際は慎重な性格です。夜行性と思われることもありますが、それは人を避けて夜間に行動するため。本来は昼行性といわれています。基本的には人がいない時間帯に行動しますが、警戒心がなくなると日中でも姿を見せることがあります。
イノシシは物語の中では愚鈍なキャラクターとして描かれることも少なくありません。十二支の昔話でも、本当はトップを走っていたのにうっかり神様の御殿の前を通り過ぎてしまい、結局最下位で到着したとされています。ですが実際はとても賢く、社会性が高いことがわかっています。研究の多くはブタを対象にしたものですが、その知能は若い人間にも匹敵し、犬より賢いといわれることもあります。野生のイノシシも学習能力が高く、木の皮を道具にして穴を掘ったり、仲間と協調して行動したりする姿が確認されています。
神の遣いや縁起物といわれることも
山岳信仰ではイノシシは山の神の使いとして崇められてきました。また白いイノシシは山の神そのものといわれてきました。狛犬の代わりにイノシシの像が置かれている神社もあります。仏教では武運の神様、摩利支天の使いとされ、摩利支天がイノシシに乗る姿が多く描かれています。またイノシシ自体が「無病息災」「子孫繁栄」の縁起物でもあります。
イノシシを見かけたらどうする?

イノシシは警戒心が高く慎重なので、もし遭遇してもたいていイノシシの方が逃げていきます。ただ、興奮させると突進してくることもあります。イノシシを刺激せず、そっとその場を離れるのが最善です。イノシシの子どもがいた場合、近くに母親がいる可能性が高いので絶対に近づかないようにしましょう。
まとめ

イノシシは適応力が高く、国内では昔から農作物を食べられる被害があり、その被害は現代でも深刻です。かつては雪が苦手といわれていましたが、今では東北の豪雪地帯にも生息地を広げています。また、人を警戒するとされてきましたが、最近では住宅街に入ってくることもあり、人との距離感も変わりつつあるようです。
こうした変化も受け止めながら、在来の野生動物との共存を考えていく必要があるでしょう。