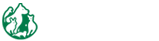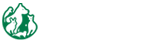by 佐藤華奈子 2024.12.26

山のそばでヤギのようなヒツジのような、不思議な野生動物を見かけましたか?それはおそらく二ホンカモシカでしょう。高山に暮らすことから山の野生動物の象徴で、なかなか出会えないため幻のどうぶつと呼ばれていた二ホンカモシカ。昨今はそのイメージとは異なり、人里までおりてくることもあります。この機会に二ホンカモシカの特徴や生態、今置かれている状況を知っておきましょう。
二ホンカモシカってどんなどうぶつ?
二ホンカモシカは本州、四国、九州の山に生息する草食動物。頭胴長は約120㎝、体高は約70㎝、体重は30~40㎏ほどになる大型の野生動物です。しっぽは10㎝ほどであまり目立ちません。角は10~15cmほどで後ろ向きに伸びています。性別や地域による体格差はありません。顔には三角形の大きめの耳があり、かわいい丸い目をしています。鼻は黒で顔回りにはフサフサの毛があります。脚が丈夫で急斜面を登ることが得意です。
毛の色は暗い灰色や明るい灰色、白に近いものや茶系などさまざまです。生息している地域によっても異なり、南の地域では色が濃く、北の方にいくと薄くなる傾向があります。東北では白いカモシカも目撃されています。
食事は木の葉や木の芽、花や実、小枝、草など。消化のために一度食べたものを口の中に吐き戻して再度咀嚼をする反芻(はんすう)を行います。早朝や夕方に採食し、日中は見晴らしが良い場所に座って反芻をしています。性格は好奇心旺盛。人間が近づいても、すぐ逃げずに興味を持ってじっと見ていることもあるほどです。
単独行動が基本ですが、生後1年間は母子で行動するほか、少数の群れになることも。行動範囲は各々で決まっていて、よく同じ場所に姿を現します。繁殖の季節は秋。およそ7ヶ月の妊娠期間を経て、4~6月に出産します。子どもは通常1頭で、2頭生まれることは稀です。赤ちゃんは生まれてすぐに立ち上がって歩くことができます。生後1週間ほどは草の陰に座って母親が授乳に来るのを待ち、やがて一緒に歩き回るようになります。
シカではなくウシやヤギの仲間

名前からシカの一種と思われがちですが、カモシカはシカ科ではなくウシ科の仲間。シカよりもウシやヤギに近いどうぶつです。近縁にあたるのは「ゴーラル」というどうぶつ。ゴーラルはアジア大陸の山岳地帯に広く生息し、ヒマラヤ山脈の急斜面も難なく登ります。姿形や体の大きさはカモシカによく似ています。カモシカとの決定的なちがいは眼下腺(がんかせん)がないこと。眼下腺は目の下にある臭腺で、カモシカはここから臭いのある液を分泌し、木などにこすりつけて縄張りを主張します。両目の下に黒い点のように見えるのが眼下腺で、成長とともに大きくなります。目と同じくらいの大きさになると、遠目に見たときに目が4つあるように見えることがあります。
カモシカは世界に3種類
カモシカ属には、日本にいるニホンカモシカのほかにタイワンカモシカ、スマトラカモシカがいます。いずれも日本、台湾、スマトラ島と生息地が限られています。日本の野生にいるのはニホンカモシカのみ。日本にしか生息していない固有種です。氷河期時代のどうぶつと同じ原始的な形態が残っているため「生きた化石」とも呼ばれています。
角は生涯伸び続ける

カモシカには性別に関係なく角があります。カモシカの角はシカのように抜けて生え変わることはありません。少しずつ伸びて年輪のように層ができるため、角から年齢を知ることもできます。
二ホンカモシカは絶滅危惧種?
二ホンカモシカは古くから狩猟の対象でした。特に大正時代には毛皮や肉、角を求めてさかんに猟が行われ、急速に数が減ってしまいました。そして目撃されることが少なくなり、幻のどうぶつと呼ばれるように。こうした状況を受けて1925年に狩猟法が改正され、二ホンカモシカの捕獲が禁止されましたが、密猟は続いていたため、1934年には国の天然記念物に。1955年に特別天然記念物に指定され、保護されました。その後、取り締まりや時代の流れに伴い密猟がなくなったこと、天敵のニホンオオカミが絶滅したこと、政策によってスギやヒノキの植地が増えて下草が食べられるようになったことで、カモシカの数は回復しました。
2024年現在、IUCN(国際自然保護連合)のレッドリストでは、ニホンカモシカは絶滅の危険は少ない低懸念(LC)に分類されています。国内でも全国的に見れば数は少なくないものの、地域によって状況が異なります。東北から中部の生息域では数が回復したことで見かけることも珍しくなくなり、人里にもおりてきて農作物を荒らすことが問題となっています。一方で近畿以西、九州や四国では依然として数は少なく、生息域も狭まって地域的に絶滅の恐れがあるところも。中国地方では絶滅しています。国内でも場所によって状況が大きく異なっているのが現状です。
また全国で二ホンジカが増えたことで、シカと競合して二ホンカモシカが生息地を追われるケースも。今は絶滅の心配がない地域でも、注意深く生息状況を見守っていく必要があることは変わりません。
カモシカを見かけたらどうする?

もし二ホンカモシカに遭遇したら、何もしないで見守ることが基本です。二ホンカモシカはおとなしいので積極的に襲ってくることはまずありません。ただ危険な相手と認識されると、角で攻撃される可能性も。「シューッ、シューッ」と鳴いているのは警戒している証拠です。騒いだりして刺激せず、自ら去っていくのを待ちましょう。二ホンカモシカが希少な地域では、目撃情報を募っているケースもあります。余裕があれば写真を撮り見かけた場所を記録しておくと良い場合もあります。
まとめ
二ホンカモシカは日本の野生動物で唯一のウシ科の仲間。数少ない大型の野生動物のひとつでもあります。カモシカの生息域は山に限られるため、範囲は広いものの分断されています。今、数が少なくなっているところで絶滅してしまうと、遺伝的な多様性が失われてしまうのです。日本にしかいない二ホンカモシカを守っていくために、まず、二ホンカモシカを理解することが欠かせません。カモシカに興味を持ったら、お住まいの地域にカモシカはいるのか、今どんな状況なのか、ぜひ調べてみてくださいね。