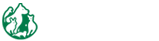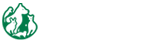2017.09.07

3億個もの卵を産卵する!?
一度見たら忘れられない、なんともユーモラスな体型。魚の頭部分だけが泳いでいるようにも見えます。そのためか、英語でヘッド・フィッシュ(頭魚)と呼ばれることもあります。
ひと口にマンボウといっても、実は、いろんな種類があります。2017年の7月には、128年ぶりに「カクレマンボウ」という新種が見つかっています。その他の種類は以下のとおりです。
- マンボウ属:
マンボウ、ウシマンボウ、ゴウシュウマンボウ - ヤリマンボウ属:
ヤリマンボウ、トンガリヤリマンボウ - クサビフグ属:
クサビフグ
それぞれ若干、形や大きさに違いがありますが、もっとも一般的なのはマンボウ属のマンボウでしょう。
このマンボウ、大きなもので体長約3m、重さ2tにもなります。全体的に楕円形で、平たい形をしています。その姿を見ればわかるように、尾びれ、腹びれがありません。体の後ろ部分に尾びれのようなものがありますが、これは舵びれと呼ばれるものです。主に進行方向を変えるときに使われるひれです。
尾びれ、腹びれがないせいか、魚なのに、泳ぎが下手です。そのため、他の魚に捕食されてしまいがちなのも特徴のひとつ。そんな大きなリスクを抱えているためか、子孫が絶えぬよう、8000万個とも、3億個とも言われる数の卵をはらみます。
ただ、産んだあとは、守ることも育てることもせず、放置したままなので、多くがマグロやカツオなどの回遊魚のエサになってしまいます。生き残って成長していくのはほんの一握りなのです。
ちなみに、マンボウの稚魚には、トゲがたくさんあり、まるで金平糖のような形をしています。親が面倒を見てくれない代わりに、自分で自分の身を守るために、トゲを生やしたのかもしれませんね。
寄生虫がいっぱい!
容姿も独特ですが、他の魚と比べて異なる点は、ウロコがないという点です。そのため、寄生虫が棲みつきやすく40種以上の寄生虫がいるといわれています。ときどき、体を横にして海面にぷかぷか浮かんでいる姿が目撃されますが、あれは体の表面についた寄生虫を、海鳥や魚に食べてもらうためともいわれています。
体は大きいのですが、小食で、1日分の必要なごはん量は、体重の1~3%。しかも主食は体のほとんどが水分であるクラゲです。体が大きいからと言って、栄養価が高いものばかりを食べているわけではないのですね。
主食はクラゲですが、甲殻類や小魚、ヒトデなども食べます。食性が豊かなので、行動範囲も海面から海底まで、実に広範囲にわたっていて、1日の移動距離が30kmに達することもありますが、泳ぐスピードは時速2~3Kmというのもマンボウならではです。
大きな体でゆったり泳ぐマンボウの姿には、癒し効果も期待できそうです。マンボウと一緒に水族館でゆっくりしてみませんか。
【マンボウ】
フグ目マンボウ科マンボウ属 Mola mola
日本沿岸をはじめ、世界中の暖かい海域に分布している。混獲などで数が減っているとして、2015年、国際自然保護連合(IUCN)が絶滅危惧種に加えた。