
犬の災害対策を考えよう② ~被災体験から学ぶ犬の防災~
2023.08.29愛犬と共に東日本大震災で被災したアニコム社員の体験談をお届けした前回。
後編ではその話のなかから5つの出来事に注目し、どのような災害対策ができるのか、考えてみたいと思います。
①窓にも脱走防止策を忘れずに
「揺れで窓が勝手に開いてしまう」
「クレセント錠」は、ごく一般的な窓の鍵。揺れの強さや長さにもよるとは思いますが、揺れで窓が開く現象は、どのご家庭でも起こりうるでしょう。
また、地震によりパニックを起こしたペットが脱走するケースは、2018年に発生した大阪北部地震や北海道地震でも数多く報告されています。同様の事故を避けるためにも、脱走をさせないための対策はとても大切です。
把手を回せなくなる補助ロックつきのものは、窓を閉める際に必ずロックもかけましょう。ロックがないタイプをお使いの場合は、防犯用の引き戸ストッパーなどを窓の鍵と併用するのがおすすめです。
②愛犬の居住空間の安全性を見直してみて
 「いつも過ごしているベッドで被災」
「いつも過ごしているベッドで被災」
愛犬のお気に入り場所は、もっとも被災しやすい場所なのかもしれません。
- まわりに倒れてきそうな家具や、落ちてきて割れるようなものはないですか?
- 窓に近い場所なら、ガラスが割れて飛び散る心配はないですか?
- 万が一被災したとき、逃げるための退路は確保できますか?
居心地がいいだけでなく、安全な環境作りをしてあげてください。
③持ち出し袋は持ち出しやすい場所に
「水やフードを持ち出すことに頭が回らなかった」
防災用品はあらかじめ用意し、玄関など避難口付近の、すぐに持ち出せる場所に用意しておきましょう。たとえば、毎日使うお散歩バッグと同じ場所に収納しておけば、いざというときにその存在を思い出しやすいでしょうし、定期的に内容物をチェックするきっかけにもなりそうですね。
車で逃げることを想定している場合は、車中にも一部避難グッズを置いておくとよいかもしれません(フードやおやつの長期保存には不向きかもしれませんが)。いずれにせよ、「パッと持って逃げるだけ」の状態にしておけば、より安全な避難ができるはずです。
④誰が一番早く愛犬の安全確保ができるか確認しておこう
「誰かがたまたま家にいたのは不幸中の幸い」
日中、犬だけでお留守番をさせているご家庭の場合、災害発生時に誰が家に戻るかなど、愛犬を救出に向かう方法を検討し、ご家族で話し合っておくとよいでしょう。避難のための移動手段に車が必須の地域は、ドライバーがいかに早く戻れるかどうかがカギを握るかもしれません。
また、ご近所にご家族や友人など信頼できる方がいる場合、帰宅できないときに愛犬の様子を教えてもらえるよう、あらかじめ約束を取り付けておくのもよいでしょう。
⑤愛犬ができるだけ“日常”を過ごせるよう備えを
 「フードのストックもあり、自宅で乗り切れた」
「フードのストックもあり、自宅で乗り切れた」
日常生活に必要不可欠なアイテムがストックされているか否かは、非常事態を乗り切るために重要です。ただでさえ災害にショックを受け、場合によっては非日常のなかでの暮らしを余儀なくされている愛犬に、なるべくストレスなく過ごしてもらうためにも、しっかり準備をしたいものです。
環境省の「災害時におけるペットの救護対策ガイドライン」などを参考に、以下のような防災リストを作ってみました。
- フードと水(5日分程度※) ★
- 器(フードや水を入れられるもの) ★
- トイレ用品(ペットシーツ、うんち袋など) ★
- ケージ、首輪、ハーネス、リード(伸縮しないもの) ★
- 普段飲んでいる薬 ★
- ケア用品(ブラシ、ウェットティッシュ、タオルなど)
- 鑑札、狂犬病予防注射済票
- 最新のワクチン証明書(混合・狂犬病)
- 自分(犬)のにおいのついたもの(クッション、毛布など)
- お気に入りのおもちゃ
- 愛犬の写真
- ペット保険の保険証
※「5日分」は、救援物資などが届くようになるまで、自力で生活をしなくてはいけない期間を想定した日数です。療法食の場合は、通常のフードに比べて手に入るまでの日数がかかるかもしれません。療法食を与えている場合は、余裕を持ってストックするようにしましょう。
上記のリストで★がついているものは、環境省のガイドラインのなかで、持ち出す際に最優先とされているアイテムです。上記すべては無理でも、★の項目は最低限そろえるようにしましょう。
前回の記事で野地さんがおすすめしていたハーネスや、ひとり遊びができるおもちゃ、長時間楽しめるおやつなども、ぜひリストに加えてみてくださいね。
なお、フードや水、トイレ用品のような消耗品をストックする際のポイントを、下記の記事で詳しくご紹介しています。そちらもあわせてチェックしてみてください。
【関連記事】
ペットの飼い主が地震に備えておくべきこと
災害時に後悔しないためにも、しつけはしっかりと
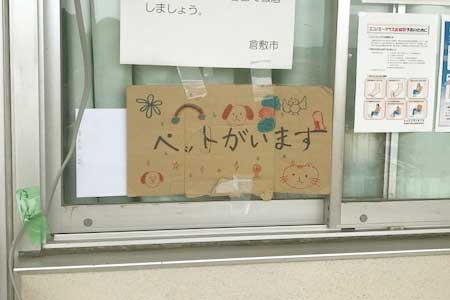 前回、「犬を連れて避難所に向かったものの、人がごった返す中、犬を連れて施設に入るのは、現実問題難しいと感じた」と語ってくれた野地さん。
前回、「犬を連れて避難所に向かったものの、人がごった返す中、犬を連れて施設に入るのは、現実問題難しいと感じた」と語ってくれた野地さん。
彼は結果として自宅で過ごすことができましたが、自宅にいられなくなった場合、愛犬がおとなしくするのが苦手などという方は、なおさら肩身が狭い気持ちになってしまうかもしれません。
大切な愛犬が行き場をなくすような事態を避けるためにも、しつけをしっかりしておくことは、やはりとても重要なのです。
災害時を想定したとき、どのようなしつけが必要になるのか、アニコムのドッグトレーナーが解説する「災害時にあなたと愛犬を守るしつけ」もぜひチェックしてくださいね。
また、吠えぐせや噛みぐせなど、何か困りごとを抱えている方は、しつけに関する過去記事もたくさんありますので、ぜひ目を通してみてください。
【関連記事】
しつけ関連記事一覧
愛犬の健康状態などを「防災手帳」に書いておこう
もうひとつ想定しておきたいのが、同行避難ができず、知人や動物病院などの施設に愛犬を預けるケースです。
愛犬の世話を他の人に託す場合、プロフィールや健康状態などを正確に伝えておくことは、預けている期間中も愛犬がなるべくストレスなく過ごすために、とても大切。あらかじめ必要事項を記したものを、防災用品のひとつに加えておくとよいでしょう。
その際は、ぜひ「アニコム オリジナル防災手帳」を活用してみてください。身体の特徴も書いておけるので、万が一愛犬が迷子になってしまった場合にも、他の人にすぐに特徴を伝えることができるはず。
そのほか、最寄りの避難所や災害時の問い合わせ先などの記載欄もあるので、この機会にご自身の居住地域の自治体の「防災・災害対策」を確認してみましょう。
1年に1回、防災用品の点検とあわせて見直しをして、内容を更新してくださいね。
▼「アニコム オリジナル防災手帳」のダウンロードはこちらから
※プリンターの設定によっては、見本どおりに印刷されない場合があります。印刷する際は、用紙サイズを「A4」、余白設定を「フチなし」、倍率を「100%」にしてください。
被災体験から学ぶ愛犬の防災、いかがでしたか?
今回ご紹介した野地さんの体験談は、あくまでひとつのケースです。きっと災害の種類やどんなタイプのワンちゃんと暮らしているかなどによって、直面する問題も、必要になることも、大きく変わるでしょう。
ぜひご自身でも、「もし愛犬と自分なら」と想像して、そこからどのような災害対策が必要になりそうか、考えてみてくださいね。
この記事がそのためのきっかけになれば、とてもうれしいです。
【関連リンク】
人とペットの災害対策ガイドライン(環境省)
【関連記事】
犬の災害対策を考えよう① ~犬と私の東日本大震災~
公開日:2019.3.8





